こんにちは、ハルです。
「10時間寝たのに、まだ眠い。これって普通なのかな?」
2022年の離婚をきっかけに、私の睡眠に大きな変化が現れました。それまでは6時間程度の睡眠で十分だったのに、突然寝ても寝ても眠い状態が続くようになったんです。朝起きても体が重くて、午後になっても眠気が取れない。まるで体の中に鉛が入っているような感覚でした。
最初は「疲れが溜まっているだけ」と思っていたのですが、この状態が数ヶ月続いた時、さすがに「これは普通じゃない」と感じるようになりました。もしあなたも同じような症状で悩んでいるなら、きっと私と同じような不安を抱えているのではないでしょうか。
【ご注意】
本記事は、睡眠の問題を経験した当事者である私の体験談に基づいています。これは医療的な助言や診断を目的としたものではありません。もしご自身や大切な人に気になる症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
寝ても寝ても眠いのはなぜ?私の体験

「寝ても寝ても眠い」という症状は、実は多くの原因が考えられます。厚生労働省e-ヘルスネットによると、過度の眠気は様々な要因によって引き起こされることがあります。私の場合、うつ病の症状の一つとして現れていました。離婚という大きなストレスが、私の睡眠リズムを大きく乱していたんです。
具体的には、以下のような症状が現れていました:
・長時間睡眠:10時間以上寝ても、まだ眠いと感じる
・朝の倦怠感:起きても体が重くて、布団から出るのが辛い
・日中の眠気:午後になっても眠気が取れず、集中力が続かない
・浅い睡眠:長時間寝ているのに、熟睡した感じがしない
・夢をよく見る:一晩中、複雑な夢を見続けている
特に印象的だったのは、「寝ているのに疲れが取れない」という感覚でした。まるで体が休まっていないような、常に疲れているような状態が続いていたんです。
寝ても寝ても眠い原因を探ってみた
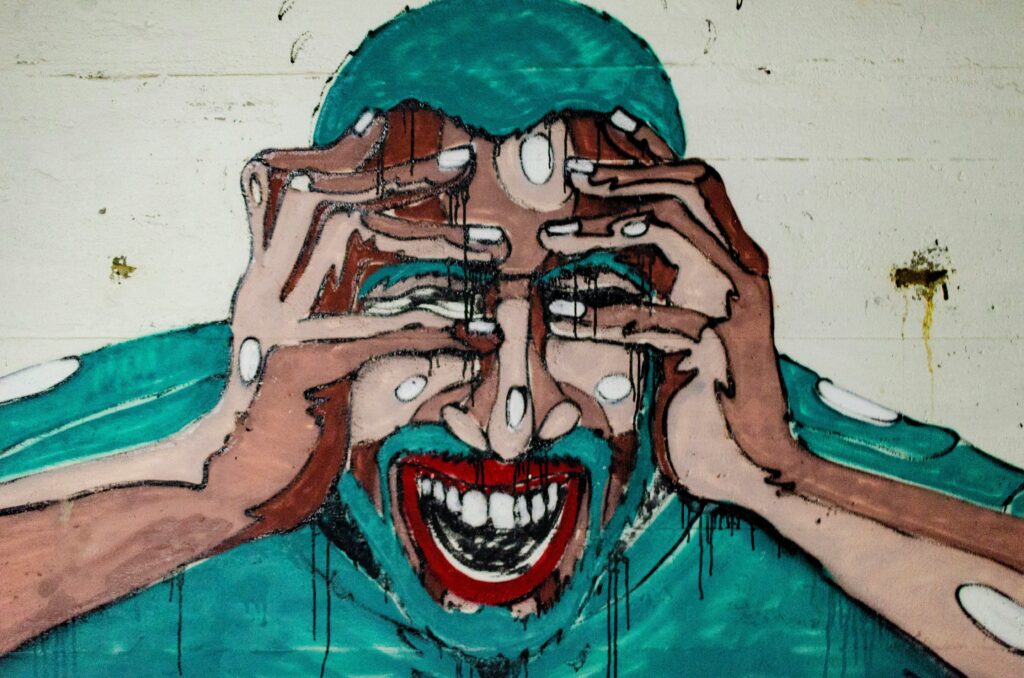
この症状が続いた時、私は自分の生活を振り返ってみました。すると、いくつかの原因が見えてきたんです。
1. ストレスによる自律神経の乱れ
離婚の手続きや将来への不安が、私の自律神経を大きく乱していました。ストレスが続くと、体は常に緊張状態になり、休息モードに入りにくくなってしまうんです。
2. うつ病による睡眠の質の低下
うつ病になると、睡眠の質が大きく低下します。長時間寝ていても、深い睡眠(ノンレム睡眠)が取れず、浅い睡眠が続いてしまうんです。そのため、寝ても疲れが取れない状態になってしまいます。厚生労働省の情報でも、うつ病と睡眠障害の関連性について詳しく説明されています。
3. 生活リズムの乱れ
ストレスで夜眠れなくなったり、朝起きられなくなったりすることで、生活リズムが大きく乱れていました。不規則な生活は、体内時計を狂わせ、睡眠の質をさらに悪化させてしまいます。
4. 運動不足
体調が悪いと、つい家にこもりがちになってしまいます。運動不足は、体の疲労感を増し、睡眠の質も悪化させてしまうんです。
私が試した効果的な対処法

「寝ても寝ても眠い」状態を改善するために、私は様々な対処法を試してみました。完璧な解決策はありませんでしたが、少しずつ改善していくのを実感できました。
1. 規則正しい生活リズムを作る
まず始めたのは、規則正しい生活リズムを作ることでした。毎日同じ時間に起きて、同じ時間に寝るように心がけました。最初は辛かったのですが、2週間ほど続けると、体がそのリズムに慣れてきました。
・起床時間:毎日7時に起きる(休日も同じ)
・就寝時間:毎日23時に寝る
・朝のルーティン:起きたらすぐにカーテンを開けて、日光を浴びる
2. 朝の日光浴
体内時計をリセットするために、朝起きたら必ず日光を浴びるようにしました。窓を開けて、5分間でも外の光を浴びることで、体が「朝だ」と認識するようになります。
3. 軽い運動を取り入れる

体調が悪い時でも、無理のない範囲で運動を取り入れました。散歩やストレッチなど、体を動かすことで、夜の睡眠の質が改善されました。
・朝の散歩:10分程度の軽い散歩
・夕方のストレッチ:体をほぐすストレッチ
・階段の上り下り:エレベーターを使わず、階段を使う
4. 睡眠環境の改善
睡眠の質を向上させるために、寝室の環境を整えました。
・温度:室温を18-20度に設定
・湿度:加湿器を使って、湿度を50-60%に保つ
・遮光:遮光カーテンを使って、部屋を暗くする
・音:耳栓を使って、静かな環境を作る
5. 就寝前のルーティン
寝る前の1時間は、リラックスできる時間を作りました。
・スマホを控える:就寝1時間前からスマホを見ない
・読書:軽い読書で心を落ち着かせる
・深呼吸:4秒で息を吸って、8秒で息を吐く呼吸法
・温かい飲み物:カモミールティーなど、リラックス効果のある飲み物
6. ストレス管理
ストレスが睡眠に与える影響を理解し、ストレスを管理する方法を学びました。
・日記を書く:その日の出来事や感情を書き出す
・瞑想:5分間の瞑想で心を落ち着かせる
・信頼できる人に相談:一人で抱え込まず、悩みを共有する
効果を実感できた変化

これらの対処法を続けて3ヶ月が経った頃、「寝ても寝ても眠い」状態が少しずつ改善されていきました。具体的には、以下のような変化を感じました。
・朝の目覚めが良くなった:目覚ましが鳴る前に自然に目が覚めるようになった
・日中の眠気が減った:午後の眠気が軽減され、集中力が続くようになった
・睡眠時間が短くなった:8時間程度の睡眠で十分に感じるようになった
・体の重さが軽減された:朝起きた時の体の重さが、以前ほど感じなくなった
特に印象的だったのは、「今日はよく眠れた」と感じる日が増えたことです。それまでは、どんなに長く寝ても「眠りが浅い」と感じていたのですが、質の良い睡眠を取れるようになったんです。
現在の状況と学んだこと
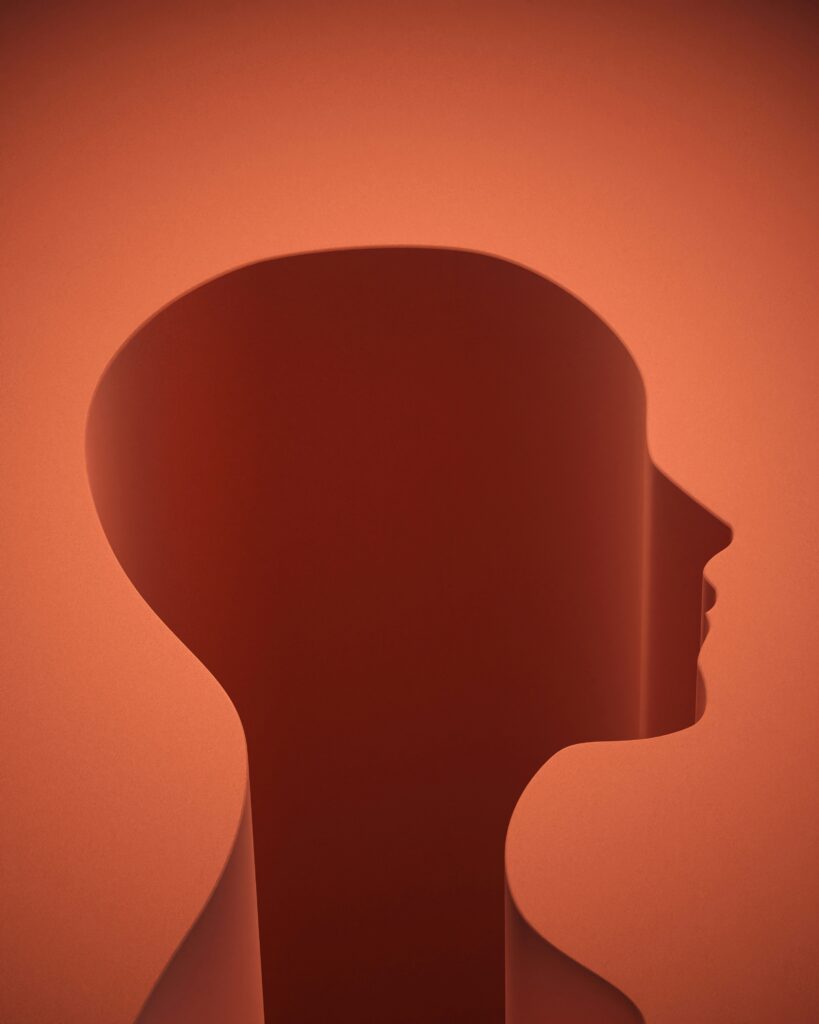
離婚から1年が経った今、「寝ても寝ても眠い」状態はほとんど改善されました。たまにストレスが溜まった時は、以前のような症状が出ることもありますが、対処法を知っているので、早めに改善できるようになりました。
この経験を通して学んだのは、睡眠は心の状態と密接に関わっているということです。体の症状は、心の状態を教えてくれる大切なサインでもあります。
もし今、あなたが「寝ても寝ても眠い」状態で悩んでいるなら、まずは自分の心の状態を見つめ直してみてください。そして、無理のない範囲で生活リズムを整えることから始めてみてください。少しずつで大丈夫です。完璧でなくても大丈夫です。
最後に、同じ症状で悩んでいるあなたへ

「寝ても寝ても眠い」という症状は、決して珍しいものではありません。私も最初は「なぜ私だけ?」と思っていましたが、実は多くの人が経験している症状なんです。
大切なのは、一人で抱え込まないことです。医師に相談したり、信頼できる人に話を聞いてもらったりすることで、必ず解決の道が見えてきます。
あなたの体は、あなたの心の状態を教えてくれています。そのサインに耳を傾けて、少しずつでも前に進んでいきましょう。
睡眠は心の鏡です。その鏡に映る自分を大切にして、一緒に前に進みましょう。



コメント